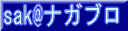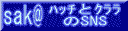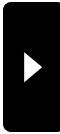遺伝の勉強のとき、親をP、子を1、孫をF2、…と書きますね。
農業をされている方はF1はよく使うようです。
PもFもラテン語が起源の言葉です。
Pは英語と同じparentです。
entは人を意味する語尾ですが、
pareは「整える」というような意味のようです。
ニュアンス的には「生み出す」「力をもたらす」のようで
画竜点睛のエピソードの「目を入れる」に近いのかもしれません。
だからparentは「子どもを生み出す人」ということですね。
pre(前もって)が付けばprepare「準備する」になります。
準備したものがpreparat「プレパラート」(ドイツ語)です。
emperor「皇帝」も元は“隊列を整える人”という意味だそうです。
compare「比較する」のpareは別物でpairと同語源です。
Fはfiliusというラテン語だそうですが
英語にも関連語彙が無いか調べてみました。
ad libとかのad(~に向かって)が変化した“af”が前にくっついて
動詞化したものがaffiliate「加入させる」だそうです。
ネットで稼ごうというあの話の“アフィリエイト”です。
元々は「養子にする」という意味から派生したんだとか。
だから「嫡出子の父親を決定する」という法律用語もあるみたい。
「“加入させる”から“認知する”」とこじつけて
覚えている人もいるかもしれませんが
やはり語源を考える方が説得力ありますね。
うちの塾も今春から予備校部門ができますが
こういう授業をやったら面白いですよね。
もし英語力があったら立候補するんですけどね(笑)