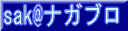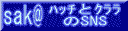今お世話になっている塾では英語の先生が産休のため
私がピンチヒッターで英語も教えています。
そんなわけで、再勉強の毎日ですが
高校生当時に気になっていて解決しなかったことが
今はインターネットのおかげで色々なことがわかります。
まぁそれでも決定打となるほど納得はできないんですがね。
その1つが、be to 不定詞です。
「義務・予定・運命・可能・意志を表す」などと習うのですが
それはbeを伴ったときに初めてそうなのでしょうか?
こちらのサイトを読んだところでは
beを伴わなくても運命などの意味を持っているように私には思えます。
こういうことを高校で教えてほしかったと思います。
おそらく中学生あたりで文中にあるto不定詞に対して
「このtoは何だ?」と質問するのでしょうが
「前置詞」と答えたらどうなるんでしょうね。