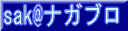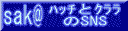私がテキスト作りを始めたのは
新卒で入った塾でですが、
今のフォーマットになったのは
その後に入った高認(大検)予備校でのことでした。
今は改善されたから暴露しちゃいますが
当時その予備校の生物のテキストが
とてもひどかったんです(笑)
ページ数もかなり少なくて
ポイント説明もかなり内容が希薄で
テキストで学んだことだけでは
問題を解けないという有り様。
生徒から受ける質問は
大概そういうテキストの不備によるものでした。
私自身、生物は受験で使ってなかった関係で
あまり得意ではない科目でしたから
勉強ついでにテキストを作っちゃおうと
始めたのがキッカケでした。
その後その予備校はかなり充実したテキストを作りました。
ちょっと聞いた話では外部に依頼したものらしく
そのためか今度は問題集の方が薄くなってしまいました。
単なるコスト削減が理由かもしれませんけど。
私の作ったテキストには
かなり問題も入れてあったので
高認の生物合格率はかなり上がったんですよ。