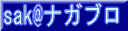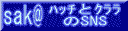これを「きょうえき」と読む生徒が多いのですが
正しくは「きょうやく」と読みます。
「後三年の役」とか「兵役」とかの
読みに引っ張られるのでしょうね。
なぜなら昭和32年まで「共軛」と書いていたからです。
国語審議会で当用漢字(今で言う常用漢字)表に
載らない漢字については別の漢字を割り当てることに
なったため今は「共役」と書いているのです。
「軛」というのは「くびき」と読み
車の轅(ながえ)の前端に渡して
牛馬の頸の後ろにかける横木のことなのだそうです。
つまり「共軛」という言葉には2個でセットになっている
様子を表したかった気持ちが込められているのです。
なんで、こんな書き換えを許しちゃったのかなぁ。

上越地域に「頸城」という地方名がありますが
なんか関係あるんでしょうかねぇ。